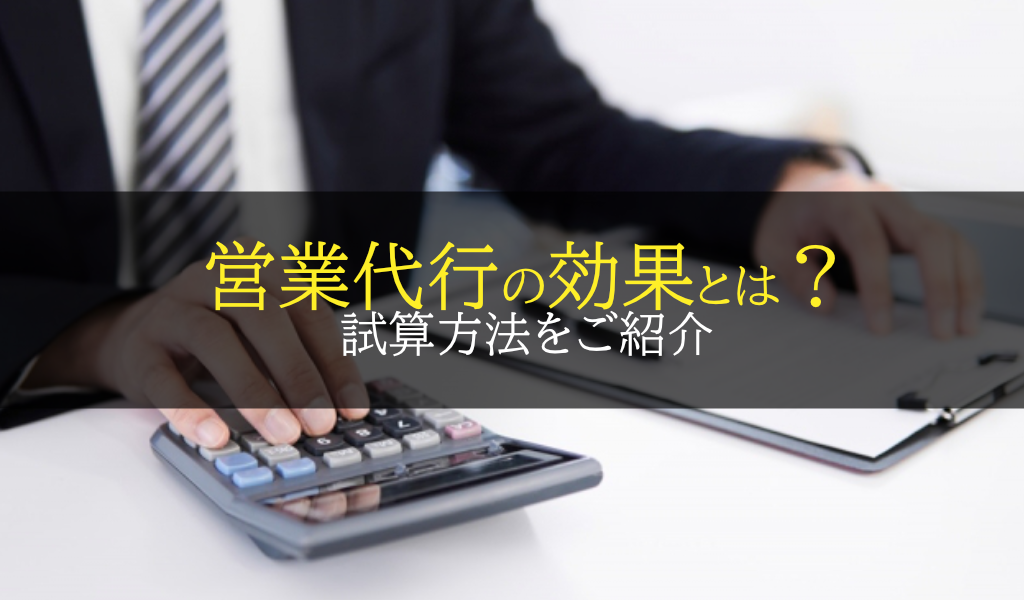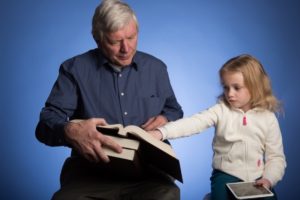編集担当 田村
編集担当 田村皆さんこんにちは!アポカレッジ編集部員の田村です。
今回は営業代行の費用対効果の試算方法について解説します。
営業代行は比較的高額な施策です。
「一体どれくらいの効果が出るのか?」が分からなければなかなか手が出せないでしょう。
そこで今回は、営業代行の費用対効果の試算方法をご紹介します。
ぜひ、自社の場合は営業代行が効果的なのかどうかシミュレーションしてみてください。
本記事は新人マーケター田村の主観を多分に含んでおります。アポカレッジ!は皆様と共にステップアップをすることを目的としたメディアですのであえてこのようなスタイルでお届けしております。情報の取り扱いは皆様の自己責任にてお願いいたします。
営業代行における「効果」とは?
まず、営業代行における効果とは何を指すのかを確認します。
これは、結論から書くと、「アポ獲得」か「受注」のどちらかとなります。
営業代行会社には、テレアポ代行会社中心にアポ獲得までに特化している会社と、提案・クロージングまで行う会社があります。
自分が依頼しようとしている会社がアポ獲得と受注のどちらを提供しているのかをチェックしたうえで、実際の試算に入りましょう。
営業代行の試算方法
それでは、具体的な試算方法を解説します。
今回ご紹介する計算方法は、その他の手法にも共通して使えるのでどの施策が一番よかったか効果測定する際にも使えます。
単純ですが試算・効果測定のどちらでも使用できるのでぜひ覚えていきましょう。
CPA
CPAとは、「顧客獲得単価」の事です。
ここでいう顧客ですが、見込み客(≒アポ)と置き換えられることもあります。
厳密な「契約した顧客の獲得単価」は後述する「CPO」になります。
総費用÷アポ獲得件数
こちらがCPAの計算式です。
仮に30万円でアポ10件なら、CPA3万円になります。
CPA3万円だとコストが割高な印象です。
受注単価が1億円を超える商材であれば良いと思いますが、月数十万円の商材ならば最低2万円は下回りたいところです。
CPO
CPOは「注文一件当たりの獲得単価」です。
CPAが時折「見込み客獲得単価」にも使われるのに対して、CPOは「注文」「契約」だけを示す指標です。
総費用÷受注件数
こちらがCPOの計算式です。
仮に30万円で受注が1件なら、CPOは30万円となります。
商材単価にもよるので一概には言えませんが、CPO30万円だと割高な部類に入るでしょう。
ROI
ROIとは「投資利益率」と呼ばれる指標です。
原価まで視野に入れて、「利益がどの程度出たのか?」をチェックする指標です。
利益÷投資額×100=(売上-製造費-(人件費+広告費))÷ 投資額×100
この計算式でROIを出すことが可能です。
売上が100万円、原価が10万円、人件費30万円、広告費30万円だったとします。
すると、
(100万円-10万円-(30万円+30万円))÷30万円×100=100(ROI)
ROI100が良いか悪いかは一概には言えませんが、0を下回ると赤字なのは確かです。
このケースだとプラスとなっているので成果自体は出ているといえるでしょう。
営業代行の効果をシミュレーション!
ここからは、架空の商材を基にシミュレーションをしてみましょう。
パッケージソフトの販売を行っているという設定で、下記の通りの成果が出たと仮定します。
予算 100万円
アポ率 1%
受注率 10%
獲得アポ数 50件
受注件数 5件
単価 100万円(年間契約)
原価 40万円
人件費 30万円
この時の各指標を計算してみましょう
CAP:100万円÷50件=2万円
CPO:100万円÷5件=20万円
ROI:{500万円-40万円-(30万円+100万円)}÷100万円×100=330
CPAが2万円、CPOが20万円、ROIが330となりました。
比較的単価が高い商材のため無事にROIが黒字で終わっています。
もし、これくらいの投資対効果が得られるのであれば導入にも前向きになれるでしょう。
CPA・CPO・ROIを見れば費用対効果はわかる!
今回は、営業代行の費用対効果の試算方法について解説し、実際にシミュレーションもしてみました。
確かに営業代行は高額の費用が掛かるので躊躇してしまいがちです。
しかし、高めの単価の商品で受注が安定的に生まれたら費用対効果は十分にあるといえるでしょう。
営業代行を検討する際の参考にしてみてください。